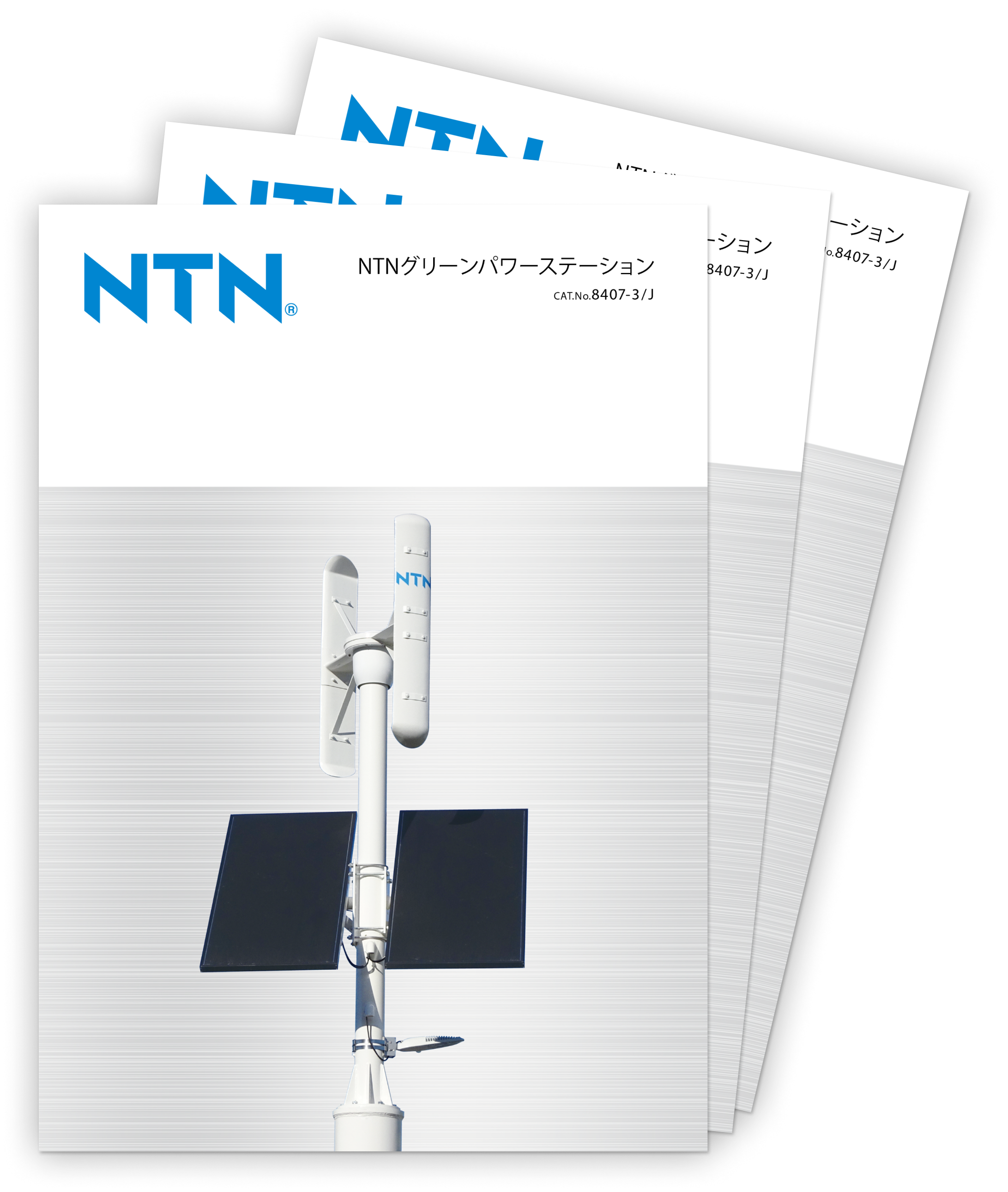カーボンニュートラルな社会を目指すためには、さまざまな領域でCO2削減に取り組む必要があります。なかでも重要な課題のひとつが、航空機を使用する際に排出されるCO2の削減です。
そこで注目されているのが、ジェット機の燃料をクリーンな燃料である持続可能な航空燃料(SAF/Sustainable Aviation Fuel)に置き換えることです。本記事では2回にわたり、SAFの概要や製造方法、現在の課題、国内外の具体的な施策、今後の展望についてわかりやすくまとめます。前編では、SAFの概要と、製造方法や現在の課題について解説しました。後編となる今回はSAFの国内外の具体的な施策や、2025年2月に「持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進に向けた官民協議会1」がまとめた最新動向について解説します※1 。
※1 出典を特に明記していないものは資源エネルギー庁「第6回 持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進に向けた官民協議会協議会」の情報にもとづく
SAFの導⼊促進に向けた取り組み
SAFの導入を促進するため、日本政府は2030年までに国内航空会社の燃料使用量の10%をSAFに置き換える目標を掲げています2。この目標達成には、国産SAFの開発・製造の推進とサプライチェーンの構築が不可欠です。特に供給側の元売り事業者等と利⽤側の航空会社との連携が重要視され、経済産業省と国土交通省は「持続可能な航空燃料(SAF)の導入促進に向けた官民協議会3」を設立し、技術的・経済的な課題について官民一体で取り組んでいます。さらに、2025年2月には最新の施策動向が発表されました。
SAFの利⽤・供給拡⼤に向けた「規制・制度」と「⽀援策」
日本では、エネルギー安全保障を確保し、持続可能なSAF市場を形成・発展させるため、供給側と需要側の両面から支援策が進められています。供給側では、SAFの製造能力と原料のサプライチェーンを確立し、国際競争力のある価格で安定的にSAFを供給できる体制の構築が求められます。一方、需要側では、航空会社が安定的にSAFを調達できる環境整備が不可欠です。
SAFの利用に伴うコスト増に対しては、航空サービス利用者の理解を得ることが重要であり、市場が未成熟な段階では、政府が初期投資を支援する政策が検討されています。その一環として、供給目標の法的設定や財政支援が進められています。
SAFに関する規制・制度
政府は「エネルギー供給構造高度化法」において、2030年のSAF供給目標を、2019年度における国内ジェット燃料の温室効果ガス(GHG/Greenhouse Gas)排出量の5%相当以上と定める方針が示されており、今後、正式に制度化される見込みです。また、国内航空会社に対しては、国際民間航空機関のCORSIA制度(国際航空のためのカーボン・オフセットおよび削減スキーム)に加え、航空法に基づく脱炭素化推進基本方針の下、2030年のSAF利用目標量が設定される予定です。
この施策により、航空会社はより明確なロードマップを持ってSAFの導入を進めることができます。
さらに、航空を利用する旅客や貨物利用者(荷主)に対して、Scope3(サプライチェーン排出量)の排出量を可視化する環境の整備を検討中です。これにより、航空業界全体の脱炭素化意識を高め、企業が持続可能な選択をしやすくなることが期待されています。
SAFに関する支援策
政府は、SAFの普及を支援するために、多様な施策を実施しています。例えば、非可食由来SAFの技術開発や実証支援、認証取得支援に対し、2024年度(令和6年度)エネルギー特別会計から約89億円が割り当てられています。
さらに、日本政府は20兆円規模のGX経済移行債を活用し、大規模なSAF製造設備の構築を支援しています。この予算のうち、5年間で約3,400億円がSAF関連設備投資に充てられる予定です。加えて、「戦略分野国内生産促進税制」により、SAFの国内生産・販売量に応じて、1リットルあたり30円の税額控除が適用される措置も導入されました。
安定的な原料確保に向けた支援策も重要であり、2023年度(令和5年度)補正予算として約1,083億円が割り当てられています。この資金は、SAFの原料となるバイオマスや廃棄物のサプライチェーン構築を支援する目的で活用されています。
産業界との連携

SAFの普及に向けた主な動きとして、①石油元売企業によるSAF製造、②原料確保に向けた活動の2つが挙げられます。石油元売企業は、国内外の技術や資源を活用し、大規模なSAF製造を目指しています。一方、SAFの安定供給には原料確保が不可欠であり、食品関連企業や自治体との連携が進められています。これらの取り組みは、日本のエネルギー自給率の向上や航空業界の脱炭素化を支える重要なステップです。
①石油元売企業のSAF製造
ある大手エネルギー企業は、海外の総合エネルギー企業と提携し、国内外から調達した廃食油などを原料としたSAFの製造を推進しています。国内の製油所跡地を活用し、CO2と水素を原料とする合成燃料(e-SAF)の技術開発も進めており、2040年までの自立商用化を計画しています。
別の石油系企業は、関東地方にある製油所にてバイオエタノールを原料としたSAFの製造を進行中で、大手電機メーカーやプラントエンジニアリング会社、航空会社などと連携し、CO2と水素から製造するSAFの技術開発および実証にも取り組んでいます。
また別のエネルギー企業は、プラント建設会社や再資源化企業と協力し、関西地方の製油所にて国内で回収された廃食油を使用したSAFの製造に取り組んでいます。
※ 「資源エネルギー庁(SAF製造に向けて国内外の企業がいよいよ本格始動)」の情報にもとづく
②原料確保のための動き
ある不動産グループは、自社が全国で運営するホテルやゴルフ場、商業施設などから発生する廃食油を回収し、エネルギー企業がSAFの原料として活用する取り組みを進めています。この連携により、廃棄物を有効活用しつつ、安定した原料供給体制の構築を目指しています。
また、別の石油元売企業と油脂メーカーは、オーストラリアの自然資源管理団体と連携し、SAFの原料となる植物「ポンガミア」の植林およびサプライチェーンの構築に共同で取り組むことで合意しました。ポンガミアは東南アジアやオセアニアに分布するマメ科の植物で、食用には不向きながら油収率が高く、持続可能なバイオ資源としての活用が期待されています。
さらに、あるプラントエンジニアリング企業は、家庭や飲食店から回収した廃食油をSAFの原料として活用する取り組みを推進しています。この取り組みは、企業や自治体、団体など幅広い主体が参加可能であり、国内の資源循環モデルの確立を目指しています。これにより、安定した原料供給を実現し、SAFの持続可能な生産に繋げていく考えです。
※ 資源エネルギー庁「SAF製造に向けて国内外の企業がいよいよ本格始動」の情報にもとづく
世界のSAF導入動向

SAFの導入は世界各国でも進んでいます。米国では、「インフレ抑制法(IRA)」による税額控除や、バイオ燃料の混合義務を定める「再生可能燃料基準(RFS)」など、企業がSAFを生産・供給しやすい環境が整えられています。欧州では、SAFを一定割合で混合することを義務付ける「RefuelEU Aviation※2」や、航空会社に温室効果ガスの排出枠を取引させる「EU-ETS」などの制度が導入されました。これにより、各国はインセンティブと規制の両面からSAFの普及を促進しています。
※2 EU域内の空港で供給される航空燃料をグリーン化する法案
米国のSAF政策と導入状況
米国では、SAFの生産・普及を促進するためのさまざまな支援策が実施されています。その代表例が「インフレ抑制法(IRA)」です。この法律では、基準値(50kgCO2/mmBtu)よりもGHG排出量の少ないSAFに対し、1ガロンあたり最大1.75ドル(約70円/L)の税額控除が適用されます。さらに、設備投資支援として、360億円以上の補助金が措置されています。
また、「再生可能燃料基準(RFS)」や「低炭素燃料基準(LCFS)」もSAFの導入を後押ししています。これらの制度では、燃料供給事業者に対して、バイオ燃料の混合や炭素強度(CI)の低減を義務付けています。SAF自体の供給目標は設定されていませんが、CIの低い燃料を供給することでクレジットを獲得し、それを他の事業者に売却して利益を得られる仕組みです。
米国では、現時点でSAFの使用を義務付ける規制はありません。そのため、インセンティブを活用しながら、各企業が自主的にSAFの導入を進めています。
EUのSAF政策と導入状況
欧州では、航空分野の脱炭素化を進めるために、さまざまな支援策が導入されています。その一つが「EU-ETS(排出量取引制度)」です。この制度では、航空会社が排出する温室効果ガスに対し、排出枠を購入する義務を課しています。しかし、一定条件を満たすSAFを使用した場合、そのバイオマス燃料部分については排出ゼロとして扱われ、さらに排出枠の追加配布を受けることができます。これにより、航空会社はSAFを積極的に活用するメリットを得られます。
また、各国の空港でもSAFの利用を促進する支援策が実施されています。例えば、ドイツのデュッセルドルフ空港では、SAF1トンあたり250ユーロ(約46円/L相当)の補助が支給されています。これにより、SAFの価格差を補いながら、航空業界での普及を進めています。
また、欧州では規制によってSAFの導入を義務付ける動きも進んでいます。その代表例が「RefuelEU Aviation」です。この規制では、2025年以降、燃料供給事業者に対し、EU域内で供給するジェット燃料に一定割合以上のSAFやe-SAFを混合することを義務付けています。この規制により、SAFの安定供給が期待され、航空業界の脱炭素化が加速すると考えられています。
SAF普及に向けた日本の今後の展望

今後SAF導入をさらに普及するためには、技術開発、投資促進策、そして供給目標の設定が不可欠です。特に日本では、エネルギー供給構造高度化法を活用し、2030年以降の具体的な供給目標が示されています。さらに、米国や欧州の政策を参考に、新たな税制措置や技術開発の支援が求められています。最後に今後の日本の動向についてまとめます。
製造に係る技術開発
SAFの製造技術は日々進化しており、特に注目されているのがATJ(Alcohol to Jet)プロセス技術です。この技術では、エタノールを原料とし、脱水によるエチレン生産と重合プロセスを経てジェット燃料を生成します。現在、ATJプロセス技術を活用した世界初の商業機向け製造プロセスが開発されており、大規模生産に向けた実証実験が進められています。
研究開発フェーズでは、ニートSAF(化石燃料を含まない純粋なSAF)の収率50%以上を目標とし、製造コストを1リットルあたり100円台に抑えることを目指しています。さらに、最先端のATJ実証設備の建設が計画されており、安定した生産体制の確立に向けて進行中です。
また、2029年度を目標にサプライチェーンを確立し、国内でのSAF生産量を大幅に増やす計画が進んでいます。これにより、航空業界の脱炭素化が加速し、持続可能な燃料の供給体制が整備される見込みです。
国内投資促進のための新たな税制措置
SAFの普及を加速させるためには、技術開発と並んで投資促進策が不可欠です。現在、米国ではインフレ抑制法(IRA)やCHIPS法、欧州ではグリーン・ディール産業計画など、戦略分野への投資を促進する産業政策が活発化しています。日本もこれに対応するため、SAFを含む重点産業への新たな税制措置の導入が検討されています。
特に、SAFのように総事業費が大きく、生産段階でのコストが高く、供給拡大に課題を抱える分野では、単なる初期投資の支援だけでなく、生産・販売段階での税額控除が必要とされています。米国では既にIRA法に基づき、低炭素燃料の生産・販売に対する支援措置が実施されており、日本も同様の制度を導入することで、国内投資を促進し、国際競争力を高める狙いがあります。
この新たな税制措置により、企業はSAFの生産・販売拡大に向けた強いインセンティブを得ることができます。結果として、革新性の高い製品の市場創出が加速し、持続可能な燃料市場の形成が促進されることが期待されています。
エネルギー供給構造高度化法におけるSAFの供給目標量の設定
日本では、エネルギー供給構造高度化法に基づき、非化石エネルギー源の利用促進を図るための施策が進められています。SAFの供給拡大に向けてもこの法律を活用し、2030年以降の具体的な供給目標が設定される見込みです。供給目標として、2019年度に国内で生産・供給されたジェット燃料のGHG排出量の5%以上をSAFで代替することが掲げられるでしょう。これは、単なるジェット燃料の置き換えにとどまらず、より高い炭素削減効果を持つe-SAFの普及も視野に入れたものとなります。
対象期間は2030年度から2034年度の5年間とされ、持続可能な燃料供給体制の確立が求められています。また、SAFのGHG削減率を50%以上とすることを目標に、原料や製造技術の開発を進める努力規定も設けられています。
こうした施策により、国内でのSAF供給体制の強化が期待されます。エネルギー供給事業者と航空業界の協力により持続可能な航空燃料の普及が進み、カーボンニュートラルの実現に貢献することが目指されています。
まとめ
2回にわたり、SAFの基本情報や製造方法、課題、国内外の動向や今後の展望について解説してきました。
SAFの普及には技術開発、投資促進策、そして政策的な支援が不可欠です。ATJプロセス技術の進展により、より効率的なSAFの生産が可能となり、新たな税制措置が企業の生産・販売拡大が後押しするでしょう。また、エネルギー供給構造高度化法の供給目標設定により、日本国内での持続可能な燃料供給体制の確立が進むことが期待されます。
持続可能な航空燃料の未来に向けて、引き続き政府と企業が連携し、国際的な動向を踏まえながらSAFの導入を推進していくことが求められます。
【出典・参考資料一覧】