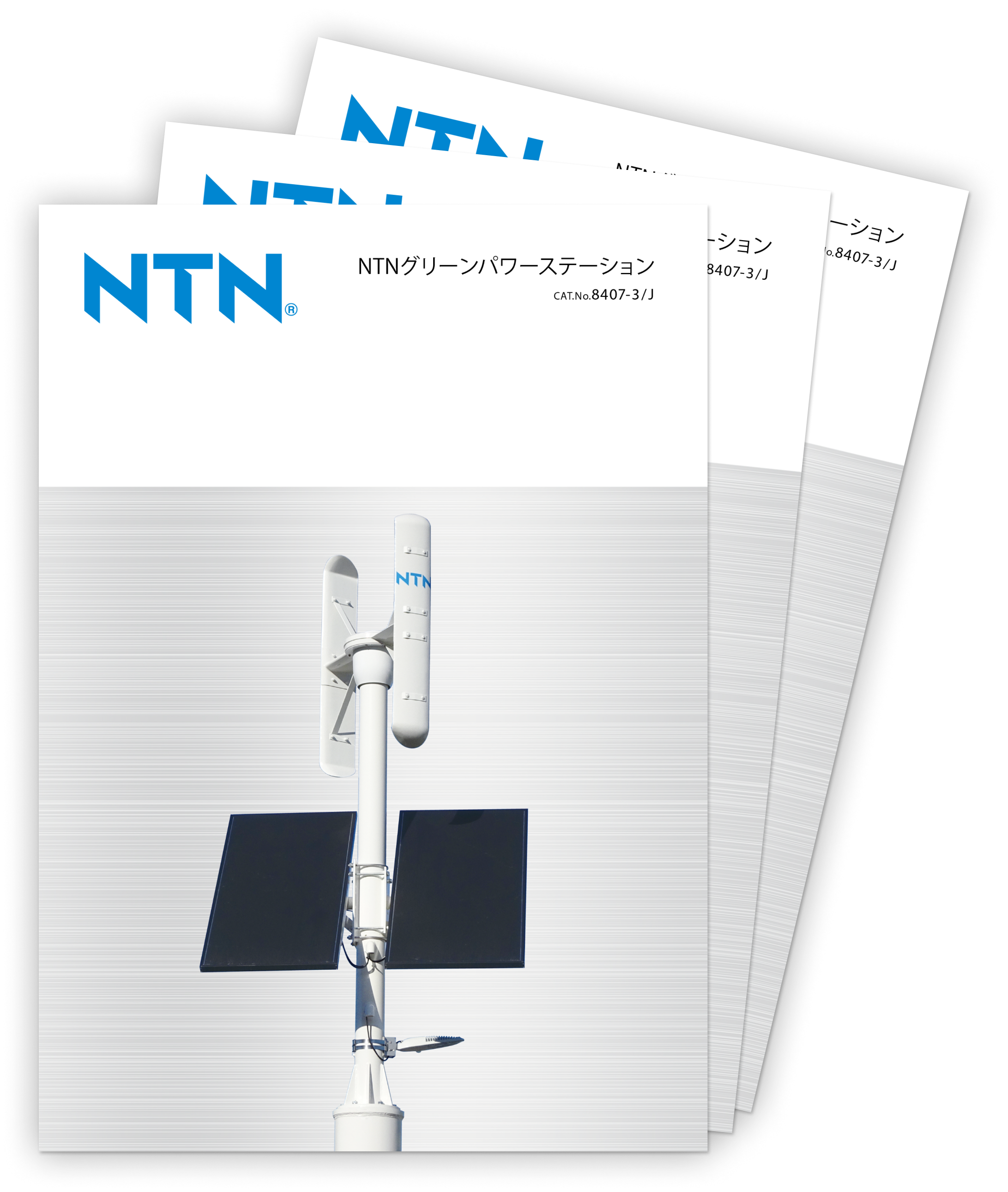半島振興法に基づき日本列島では23地域が半島振興対策実施地域に指定されています(2025年2月現在)。近年、半島地域では地震の被害が大きく、防災強化の必要性が増しています。この記事では、防災強化に向けた半島振興法改正の動きと半島自治体独自の防災への取り組みについて詳しく解説します。
半島とは?
半島は三方を海で囲まれ、一方が陸続きの土地を指し、例えば、日本列島では紀伊半島や能登半島などが有名です。日本もアジア大陸から伸びた半島として知られています。
半島と地震の関係
半島は地震の影響を受けやすい地域です。その理由は、複数ありますが、一つは半島が地震が発生するプレート境界に位置することが多いからです。特に日本は、ユーラシアプレートやフィリピン海プレートなど複数のプレートが交わる場所にあるため、地震が頻発します。
また地殻の構造も地震に関係しています。半島が存在する地域は、地殻の力が集中しやすい場所であることもあり、海底から陸地に至る地殻の境目で力が集中しやすく、地震の震源が浅い場合、半島周辺で特に大きな揺れが観測されることがあります
また地盤の特徴として、半島は海や河川の堆積物が多く、地盤が緩い場所もあります。こうした地盤は揺れを増幅しやすく、地震の際に影響が大きくなりやすいとされています。
能登半島地震の被害と特徴
2024年1月1日、石川県の能登半島でマグニチュード7.6の地震が発生しました。最大震度7の激しい揺れが志賀町と輪島市で観測され、その揺れは北海道から九州までの広範囲で感じられました。地震の特徴としては、余震が長期間続いたことや、震源が浅かったことが挙げられます。それにより被害が拡大したほか、復旧にも時間がかかっており、現在も支援活動が続いています。
能登半島地震の被害
能登半島地震は、多くの建物に甚大な被害をもたらしました。住宅や商業施設は倒壊し、中には全壊した建物も少なくありませんでした。特に古い建物は耐震性が低く、被害が大きくなりました。また、地震に伴う土砂崩れや道路の崩壊も発生し、交通網が寸断されました。このため、救援活動や物資の輸送が遅れ、人々の生活に大きな影響を与えることになりました。さらに、水道や電気などのライフラインも停止し、復旧には長い時間がかかりました。
能登半島地震の被害が大きかった理由
能登半島地震の被害が大きかった理由の一つは、震源が浅かったことです。震源が浅い地震は揺れが強く、広範囲に被害が及びやすくなります。また、古い建物も多い地域では、建物の耐震対策が不十分でした。さらに、本震後に強い余震が続いたため、二次災害も発生しました。土砂崩れや建物の追加倒壊がこれに該当し、被害がさらに拡大しました。このような要因が重なり、能登半島地震の被害は深刻なものとなったのです。
直接死を上回る災害関連死
最新の情報では、能登半島地震では、災害関連死の人数が直接死のそれを超えました。災害関連死とは、地震そのものによる死亡ではなく、災害による負傷の悪化や避難生活による身体的・精神的負担による死亡を指します。例えば、避難所生活のストレスや急激な環境の変化による体調不良の原因によるものです。高齢者や持病がある人々にとって避難所での生活は負担が大きく、健康が悪化することも多いため、防災対策にはこのような間接的なリスクへの対策も重要です。
半島振興法とは?

今回被災した能登半島は名前の通り日本にある「半島」であり、半島振興法とは、そのような日本の特定地域、特に半島部分の経済や生活環境の改善を目指す特別な法律です。これはもともと、過疎や高齢化などの課題に直面している半島地域を活性化させるために制定されました。地域特性を活かした振興策を施行し、住民生活の質を向上させることを目的としています。この法律により、地元の産業振興や観光振興策、インフラ整備などが支援されています。
半島振興法におけるメリット
半島振興法の最大のメリットは、地域の経済活性化です。地元産業の振興により、新しい雇用が創出されます。これにより、地域住民の所得向上が期待できます。さらに、観光資源の開発や、観光客誘致の促進により、地域の魅力が向上します。現在、この地域活性化に「防災強化」の観点を取り入れていくことが検討されています。
半島振興法における税制優遇措置や補助金について
半島振興法においては、税制優遇措置や補助金制度が充実しています。具体的には、特定の事業に対して税金の軽減や免除が適用されます。例えば、新規事業を開始する際や設備投資を行う場合に、法人税や地方税が減免されるのです。さらに、地方自治体から補助金が支給されることもあります。前述のように、今後は防災強化に関する項目を追加することが検討されているため、防災関連事業についても地方税の減税措置が適用されるかもしれません。
半島振興法にはなぜ期限があるのか
半島振興法には有効期限(2025年3月31日)が設けられています。この理由は、政策の効果を検証し、必要に応じて見直しや改善を行うためです。法の施行期間中に経済状況や地域のニーズが変化することが考えられます。今回注目されている防災強化に関する項目の追加も、その一例です。この方式により、半島振興のための政策が常に最適化されています。
半島振興法改正の背景と効果への期待

半島地域の現状と課題
半島地域は、過疎化が深刻な問題となっています。人口流出が続き、若者が少なくなっていることが背景にあります。また、公共交通機関が不便で、住民の移動が制約されます。加えて、高齢化も進んでおり、介護サービスの需要が増える一方、医療施設や介護施設が不足しており、生活がし辛くなっています。これらの課題を解決するためには、インフラの整備や農業、漁業などの基幹産業も振興させることが求められています。
振興法改正に向けて協議されているポイント
半島地域の持続的な発展を実現するため、地域の「強靭化」と「産業・観光振興」を柱とする振興法改正の必要性が協議されています。特に、能登半島地震を契機に、交通基盤(道路、空港、港湾等)や産業基盤(漁港、農業水利施設等)の防災回復力の向上、防災計画の見直し、災害応援協定の整備など、ハード・ソフト両面からの対応が求められています。
また、地域の独自資源を活用した産業振興も重要な課題であり、食を中心とした産業振興施策を推進し、地域経済に利益が還元される仕組みが引き続き議論されています。さらに、地域資源を活かした産業振興と観光振興を支える物流の安定化を図ったり、再生可能エネルギーや地域資源を核として、地域内での経済循環を促進することで、地域の自立的な発展を目指すことも協議されています。1
改正による期待される効果
半島振興法の改正で「防災強靭化」が盛り込まれることにより、以下の効果が期待されています。
一つ目はインフラの耐災性向上です。道路、港湾、空港などの重要なインフラの耐震性が強化されることで、災害時の孤立防止や早期の復旧が可能となります。能登半島地震などの教訓を踏まえ、救援活動を円滑にする体制が整備されることが期待されています。
二つ目は、地域住民の防災体制の強化です。自主防災組織の活動促進や避難計画の策定が進むことで、住民が迅速に安全な行動を取れる環境が整います。また、食料や水などの備蓄体制や非常用通信設備の設置が進むことで、半島特有のリスクに対応した自助・共助の仕組みが強化される可能性があります。
三つ目は、半島地域の復興力強化です。災害後の復旧を迅速に行うための事前準備が進むほか、地域経済や観光産業の回復を支える対策も期待されています。特に、津波や地震に強い都市計画が推進される可能性があります。
半島における各自治体の防災強化への取り組み

半島振興法の改正が検討される中、半島地域の自治体も独自の防災対策に取り組んでいます。特に地震や津波への防災対策はとても重要となるため、自治体ごとに住民の安全を第一に考えた特有の対策が行われています。また、地域ごとのリスクに応じた教育も通して、住民の防災意識を高めています。
房総半島に位置する千葉県では、独自性のある地震防災対策の一例として、次の2つの取り組みが行われています。
一つは、防災情報システムの整備です。千葉県は、クラウドベースの防災情報システムを導入し、県庁、市町村、消防本部、土木事務所などが情報を共有しています。このシステムは、スマートフォンからの災害報告機能や画像添付機能も備えており、迅速かつ効率的な情報収集と共有を可能にしています。また、避難情報やハザードマップを公開する防災ポータルサイトや「ちば防災メール」の配信も行っています。2
二つ目は、地震被害想定の可視化と耐震の強化です。
千葉県では地域ごとの地震被害想定を詳細に分析し、それに基づいた耐震化の促進を進めています。また、防災パンフレット「ちば地震防災ガイド」により、住民向けの防災知識を普及させています。3
半島住民の意識向上と防災意識の浸透

半島住民の防災意識の浸透や向上は非常に重要です。日常生活の中での防災意識を高めるために学校教育に取り入れたり、学校や地域のイベントで防災教育を行い、子どもから大人まで幅広い世代が防災知識を身につけることが大切です。また、地域コミュニティの活動も重要になります。防災リーダーの育成や自主防災組織の活動を通じて、住民が自ら防災活動に参加することが奨励されます。さらに、情報の共有も欠かせません。防災情報を迅速かつ正確に伝えるための仕組みが必要です。上記の自治体の取り組みのように、地域にあった防災対策に取り組む自治体が増えることで、半島地域における防災対策がまた一段と改良され、自治体と住民の備えと意識が向上するでしょう。
【出典・参考資料一覧】
- 【1】国土交通省「半島振興対策本部会 中間とりまとめ配布資料(中間とりまとめ)」 ↩︎
- 【2】千葉県「防災情報システム」 ↩︎
- 【3】千葉県「「ちば地震防災ガイド」について」 ↩︎