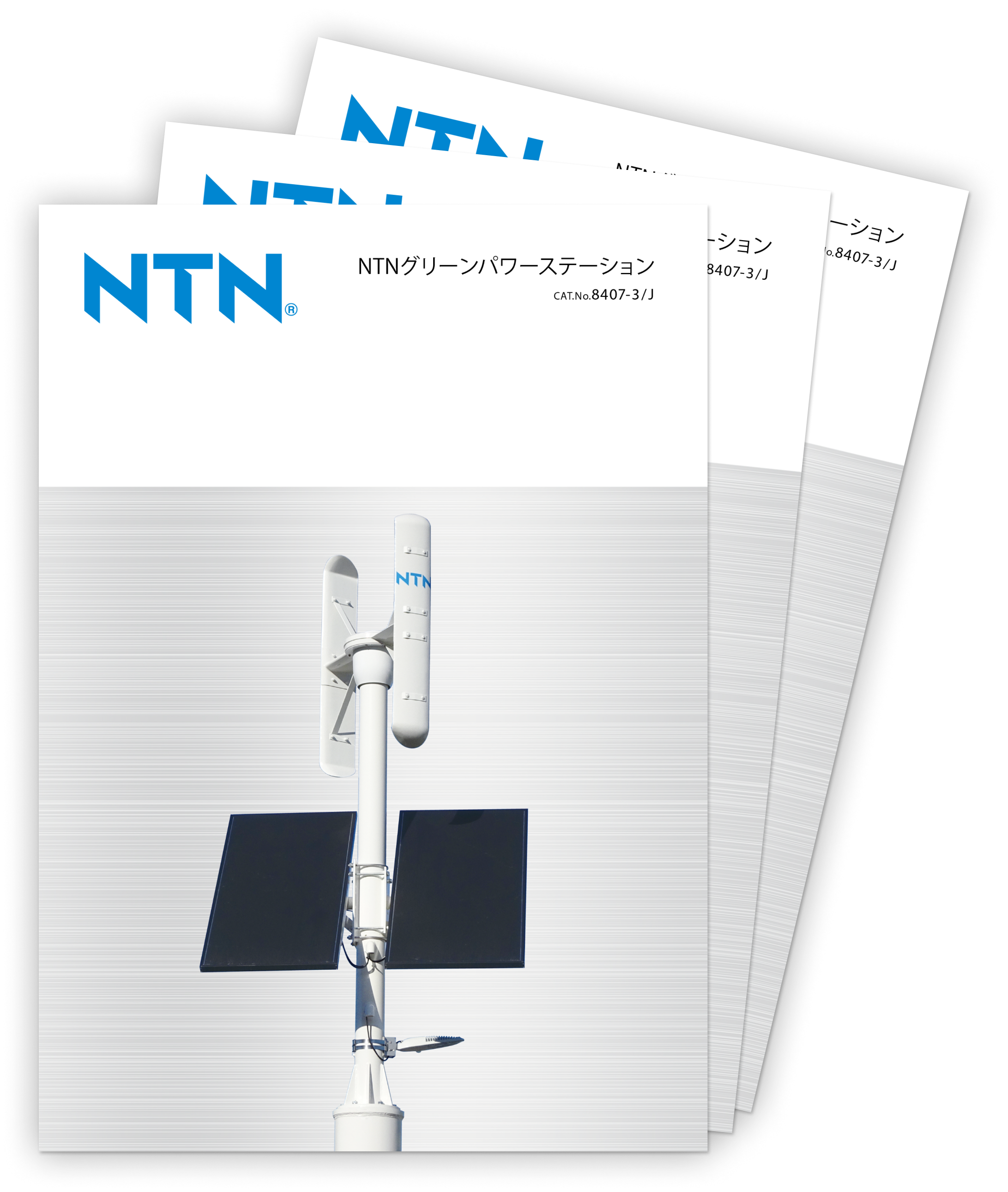日本全国に広がる「道の駅」は、1993年の制度創設から30年が経過し、単なる通過点から地域の魅力を発信する拠点へと進化を遂げています。当初は道路利用者へのサービス提供を目的としていましたが、現在では地域活性化や観光振興の一翼を担い、多くの駅が目的地として選ばれる存在となりました。この「道の駅」の発展は、第1ステージから第3ステージへと段階的に進んでおり、特に2020年以降は「地方創生・観光を加速する拠点」を目指す新たな挑戦が始まっています。本記事では、地域と一体化した戦略的な取り組みや、国と連携した支援体制の重要性について、「道の駅」第3ステージ推進委員会の中間レビューと今後の展望1を基に解説します。「道の駅」が切り拓く未来の地域創生の姿に迫ります。
「道の駅」の歴史
1993年に制度創設された「道の駅」は、地域社会と道路利用者を結ぶ拠点としてスタートしました。初期段階である第1ステージでは、主に道路利用者が安心して休憩できる場所としての役割を担いました。しかし、30年の歴史を経て、その役割は大きく変化し続けています。
2013年から始まった第2ステージでは、「道の駅」は単なる通過点ではなく、地域の観光資源や地元産品を活かし、地域振興の場として発展しました。この時期、多くの「道の駅」が地域住民や観光客にとって目的地となり、地域経済の活性化に大きく寄与しました。
そして2020年からの第3ステージでは、さらなる挑戦が始まっています。この新しい段階では、「地方創生・観光を加速する拠点」を目指し、防災機能や地域交通のハブ機能を強化するなど、「道の駅」の役割が一層高度化しています。2023年に策定された国土形成計画や国土強靭化基本計画では、防災拠点としての「防災道の駅」の推進が明確化され、災害時にも利用可能な高付加価値コンテナ2の活用などが進められています。
さらに、「道の駅」は次世代の交通インフラとしても期待されています。例えば、デジタルライフライン全国総合整備計画では、自動運転サービスの拠点やドローン航路の整備が検討され、地域交通の中核として機能する未来像が描かれています。また、「WISENET2050」では、地域のにぎわい創出を目指した新たな戦略が進行中です。
第3ステージで目指すもの

「道の駅」第3ステージは、2020年に「世界ブランド化」「防災拠点化」「地域センター化」という3つの姿を目指し、2025年度末までの目標値を設定しました。以下にその内容を簡単に紹介します。
1. 世界ブランド化
「道の駅」を世界に向けた観光拠点として発信する取り組みが進行中です。多言語対応やキャッシュレス決済の導入を進め、海外プロモーションを強化しており、2025年までに外国人観光案内所の認定率を80%以上に引き上げる目標が掲げられています。
2. 防災拠点化
新たに導入された「防災道の駅」制度により、地域防災計画に位置付けられた道の駅は、災害時における広域的な防災機能を担います。BCP策定やAI技術を活用した災害対応の強化により、地域住民や観光客に安心の提供を進めています。
3. 地域センター化
子育て支援施設やボランティア活動の場として、地域の多世代が集い活躍できる拠点を目指しています。また地域活性化プロジェクトを通じて、地元大学や企業との連携を促進し、新しい地域価値の創出を推進しています。
地方創生・観光の加速に向けた課題
一方、「道の駅」は施設の老朽化や利用者ニーズの変化といった課題にも直面しています。車中泊需要の増加に伴うトラブルや、ドローン配送拠点としての活用など、新しい社会的要請への柔軟な対応が求められています。また、現場での課題解決能力向上や、リニューアルへの対応も急務です。
社会的課題への対応
現代社会が直面する課題には、物流の2024年問題や地域間格差、災害対応などが含まれます。「道の駅」では、これらの課題に対応するための具体的な取り組みが進められています。
例えば、ドローン配送や自動運転技術を活用した次世代の物流網構築が進行中です。中山間地域ではドローンポートの整備が進められ、将来的には地域住民や観光客にとっての利便性向上が期待されています。また、防災面では、「防災道の駅」が全国で拡充されており、AIや最新技術を駆使して広域防災の核となる取り組みが進められています。
「道の駅」に求められるニーズへの対応
多様化する利用者ニーズに応えるため、「道の駅」では柔軟な施設構成が求められています。車中泊需要の増加に対応するための駐車スペース整備や、シャワー、ランドリー、無人販売機などの休憩施設の拡充が進められています。また、自家用車だけでなく公共交通でのアクセスを前提とした施設計画や、滞在型観光を促進する「人中心」の「道の駅」の実現も検討されています。これらの取り組みは、地域観光振興の新しいモデルとしても注目されています。
全国ネットワークを活かした現場支援
各「道の駅」が抱える課題は個別的かつ多様であり、全国的な連携と支援が欠かせません。全国道の駅連絡会では、「道の駅」アドバイザー制度や専門家の派遣を通じて、現場での問題解決を支援しています。また、全国「道の駅」駅長サミットやシンポジウムを開催し、事例やノウハウの共有を推進しています。さらに、出版物やデジタルアーカイブを活用し、情報の普及と共有に努めています。
能登半島地震の教訓と「防災道の駅」が果たす新たな役割

能登半島地震は、地域社会に大きな影響を与えるとともに、「道の駅」の災害対応力について重要な教訓をもたらしました。「防災道の駅」は地域防災の要としての役割を担い始めていますが、その機能強化と普及が課題として浮き彫りになっています。
「防災道の駅」とは?
「防災道の駅」は、国土交通省が選定する広域的な防災拠点で、地域防災計画に位置付けられています。災害時には、緊急支援物資の集積拠点や災害対応部隊の参集拠点としての機能が求められます。また、災害時には避難場所としても利用されることが多く、その対応力が期待されています。能登半島地震でも多くの避難者が「防災道の駅」に集まったことから、避難対応を想定した柔軟な運用が求められています。
能登半島地震での「防災道の駅」の課題
能登半島地震では、「防災道の駅」が全国に39箇所しかないという数の不足が問題視され、災害対応の拠点として十分な数が確保することが課題として挙げられています。また、利用者の間で「防災道の駅」の役割が広く認知されていないことがオペレーションの遅延を引き起こしており、認知度向上も必要です。さらに、一部の「道の駅」が災害で大きな被害を受けており、施設自体の強靭化も急務となっています。このような状況を受け、委員会ではいくつか取り組みの方向性が議論されました。
防災道の駅どうしのネットワーク化
一つ目は、「防災道の駅」同士のネットワークを構築することです。先述の通り現在、「防災道の駅」は全国で39箇所が選定されていますが、広域的な支援を行うにはその数は十分ではありません。今後、選定基準の見直しとともに防災道の駅を追加し、全国的なネットワークを構築することが重要です。このネットワークは、防災道の駅だけでなく、防災機能を有する他の道の駅も含めた組織的な人的ネットワークとして機能するもので、平時からネットワークを強化し、ノウハウを共有することで、災害時の迅速かつ効率的な対応が可能になります。
災害時の連携オペレーションの充実
二つ目は、災害時オペレーションの強化です。災害時における効果的な支援活動には、戦略的な連携オペレーションが不可欠です。能登半島地震では、高付加価値コンテナやドローンを活用した支援が一定の成果を挙げましたが、その運用計画や配備状況の事前把握が不十分だったことが課題として挙げられています。平常時において防災訓練を強化し、自治体や民間保有の資機材を含めた運用計画を事前に確立することで、災害発生時の混乱を防ぐことができます。
半島部や地形的制約のある地域への迅速支援
三つ目は、地形的制約のある地域での迅速な支援です。能登半島地震のように、半島部や直轄国道がない地域では、災害時の復旧や支援が遅れる傾向があります。これらの地域では、陸海空からの支援拠点として「道の駅」の活用が鍵を握ります。災害発生時には、ドローンを活用した被災状況の可視化や、ヘリポートとしての駐車場利用など、地形的制約を克服する手段が必要です。また、被災自治体の事務負担を軽減する仕組みを整えることで、迅速な支援活動を可能にすることができます。
地域の未来を創る「道の駅」モデルプロジェクトの重要性と成功事例
「道の駅」第3ステージ推進委員会では、第3ステージの掲げる「まちぐるみの戦略的な取組」を進める自治体と「道の駅」を応援したり、他の「道の駅」へ展開するための知見を紹介する目的で、モデルプロジェクトを実施しています。以下にその例をご紹介します。
1. 道の駅「もてぎ」(栃木県茂木町)
道の駅「もてぎ」では、茂木町とはどういう「まち」なのか、どういう魅力があるのかを、ICT・データ活用による顧客分析、住民や関係者等との議論を経て、自分たちの地域価値を再定義しました。第3ステージを体現するリニューアル工事に着手し、2026年度に新装開業を目指しています。このように、「道の駅」の中心に地域の魅力を発信する場を設置するなど、新しい地域拠点としての役割を強化しています。

右:道の駅「もてぎ」の農家の「顔」が見える売り場3
2. 道の駅「とみうら」(千葉県南房総市)
道の駅「とみうら」では、市内の8つの「道の駅」が連携し、地場産業と観光の一体的推進を実施しています。市内8つの「道の駅」を集荷拠点とし域内物流の仕組みを構築し、2つの「道の駅」に6次産業施設(枇杷加工場、生乳加工場)を設置しました。新たに地元野菜や果物を原材料とした菓子製造機能を加えるなど地域全体の6次産業化を推進しています。

今後の「道の駅」第3ステージの方向性
「道の駅」単体から「まちぐるみ」への進化
第3ステージの最大の特徴は、「道の駅」を地域全体の課題解決の拠点とする「まちぐるみ」の取り組みへの進化です。これには、自治体、地域住民、地元団体、民間企業、国など、多様な主体が連携することが欠かせません。官民ハイブリッドな特性を活かし、「道の駅」を核とした戦略的な「しかけ」を構築することで、地域課題に包括的に対応します。
国の支援枠組みの強化
「道の駅」第3ステージの成功には、国による支援体制の強化が欠かせません。関係省庁横断的な支援を進めるとともに、地域ごとの課題や魅力を掘り下げるため、全国道の駅連絡会を中心としたアドバイザーの派遣や相談窓口の設置が推進されています。また、「道の駅」第3ステージ応援パッケージ(仮称)として、地域の成熟度に応じた伴走型支援が提案されています。この支援枠組みは、予算措置や制度活用を含む包括的なサポートを提供し、地域の取り組みを後押しします。
まちぐるみの価値再定義
「道の駅」を中心に、地域全体での議論を通じて地域価値を再定義する取り組みも重要視されています。これには、顧客視点での分析や地元の資源を活かした戦略の策定が含まれます。例えば、来訪者データの活用や地域資源の再発見を通じて、観光地や生活拠点としての魅力を高めるプロジェクトが展開されています。
「道の駅」第3ステージに期待されていること
「道の駅」は第3ステージを通じて、単なる道路利用施設を超えた地域課題解決の核として進化しています。地域住民や観光客にとっての利便性向上に加え、防災や物流、観光振興といった多面的な役割を果たしつつあります。また、国の支援体制や官民連携を活かし、地域ごとの特色や課題に応じた柔軟な施策を展開することで、持続可能な地域社会の実現を目指しています。この取り組みがさらに広がることで、「道の駅」は地域経済を支える中核的存在となり、地域住民にとって欠かせない存在へと進化するでしょう。今後の展開に注目が集まる中、「道の駅」が描く未来の地域社会への貢献が一層期待されています。
【出典・参考資料一覧】