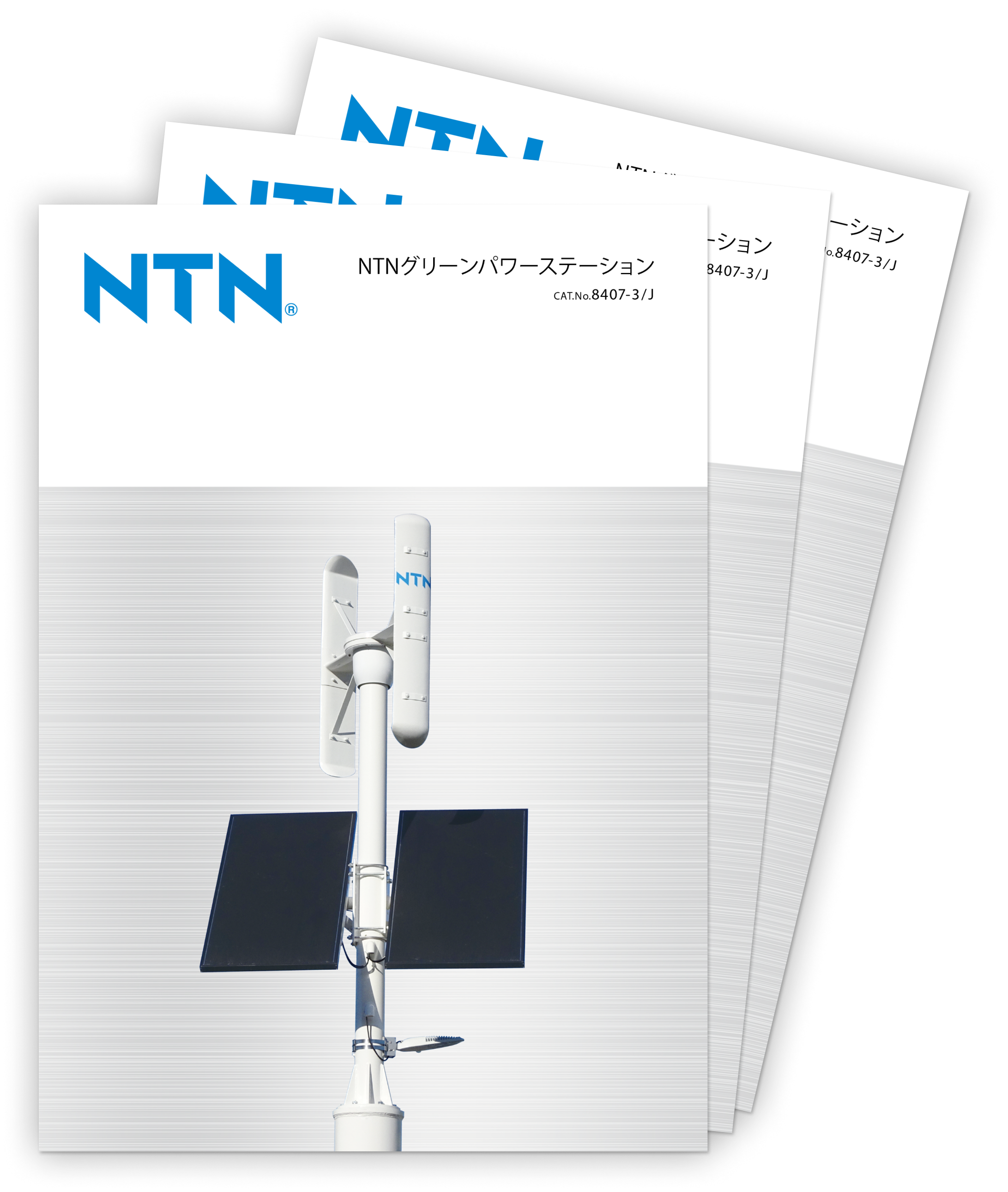2022年4月に導入されたFIP(Feed-in Premium)制度は、再生可能エネルギー(以下、再エネ)の発電事業者の収益を電力市場価格に連動させる仕組みで、需給に応じた電力供給を促進し、再エネの電力市場への統合を推進する重要な役割を担っています。2024年3月末時点で、FIP認定量は新規認定・移行認定を合わせて約1,761MW(1,199件)に達し、一定の成果を挙げています1。
しかし、将来的には全ての再エネ電源をFIPへ移行させることが望ましく、さらなる活用促進のためには事業環境の整備が欠かせません。
本記事では、政府が公開した再エネ主力電源化アクションプラン(案)2で示されたFIP制度の更なる促進の詳細を解説し、政府の取り組みや具体的な施策をご紹介します。
出力制御ルールの見直しが進行中
政府は、再エネの最大導入を目指し、優先給電ルールの見直しを進めることをアクションプラン(案)に盛り込んでいます。具体的には、FIT(Feed-in Tariff)電源を優先的に出力制御し、FIP電源への移行を後押しする方針です。さらに、FIP電源への移行を促進するため、蓄電池の活用や発電予測技術の支援を強化することで、FIP電源の活用比率をまず25%まで引き上げることとしています。
これにより、FIP電源(太陽光発電と風力発電)は当面の間、出力制御の対象とならず、FIT電源の出力制御確率は増加することが期待されます。
事業環境整備の更なる推進
FIP電源における更なる情報開示の推進
政府は、FIP制度の活用をさらに促進するため、再エネ発電事業者や金融機関等の関係事業者に有用な情報を開示していくことは、事業の予見性を高めるために重要です。具体的には、プレミアム交付額に関連する参照価格や市場価格の実績データをエリア別・月別に開示することです。また、出力制御の長期的な見通しも試算し、公表することです。
FIP併設蓄電池における系統充電の拡大
FIP電源に併設される蓄電池について、これまで発電設備からの充電のみが認められていましたが、系統(電力網)からの充電も可能とすることで、蓄電池の稼働率が向上し、より効率的かつ効果的に需給バランスの確保に貢献できるようになります。
また、蓄電池から供給される電力が系統由来ではなく、認定発電設備由来であることを計算するための基準式も同時に策定されました。
現在、この措置の対象となるのは2024年度以降に新規認定を受けたFIP電源のみですが、FIP移行案件の増加を受け、2023年度以前に認定を受けたFIP電源(FITからFIPに移行したものを含む)にも適用が拡大される予定です。
FIP移行案件の事後的な蓄電池設置時の価格算定ルール
再エネ発電事業の効率化と国民負担の抑制を両立するため、2023年度から事後的な蓄電池設置に関する新たな価格算定ルールが適用されています。このルールは、2021年以前にFIT認定を受けたFIP移行案件を対象に、蓄電池をPCS(パワーコンディショナー)よりも太陽電池側に設置した場合、発電設備の出力に基づいて基準価格(蓄電池設置前価格と十分に低い価格※1)を加重平均した値に価格変更するものです。これにより、蓄電池設置後の基準価格は、設置前の価格よりも十分に低く抑えられる設定となります。
しかし、事業者団体からは、この算定ルールは実際の電力潮流より過小に価格算定しているとの指摘があり、2024年8月末時点では当該ルールの適用事業者がいない状況となっています。このため、実態に即した算定方法を導入し、蓄電池設置をさらに促進するための見直しが進行中です。
現行の算定方式を改め、過積載率(太陽光パネルの出力 ÷ PCSの出力の割合)に基づいた新しい方式により、実態に即した価格に設定することで、国民負担を抑えつつ、FIP移行案件での蓄電池設置がさらに後押しされることが期待されています。
※1 経済産業省が将来的に目指す市場価格よりも低い価格
FIP電源における供給シフトの円滑化
FIP電源を円滑に供給シフトさせるためには、発電量予測技術の向上や蓄電池の活用を促進するための事業環境の整備が重要です。制度開始当初の2022年4月から、FIP事業者に交付されるプレミアム(供給促進交付金)にはバランシングコスト(再エネ発電における計画値と実績値の差を補うための費用)が上乗せされています。
また、事業者がコスト削減のインセンティブを持つ仕組みを維持しながらも、FIP制度の活用をさらに促進するため、バランシングコストの時限的な引き上げを実施しました。
さらに、FIT電源とFIP電源間の公平性を確保するため、出力制御順の変更が計画されています。この変更により、FIT電源の出力制御確率(発電を停止させる確率)が増加し、買取量が減少することで国民負担が抑制される効果が期待されています。
さらに、蓄電池の活用や発電予測技術の支援強化策として、バランシングコストのさらなる時限的な引き上げが検討されています。今後は、措置の対象範囲や期間、交付額の具体的な条件について、調達価格等算定委員会で詳細が議論される予定です。
非化石証書(非FIT証書)の直接取引の拡大
FIP制度では、再エネ発電事業者が自ら環境価値を販売する仕組みが設けられており、特に非FIT証書の売却を容易にすることで、FIP制度の促進に繋がると考えられています。
非FIT証書は通常、小売電気事業者が高度化法義務達成市場(小売電気事業者が非化石電源比率の目標を達成するために非化石証書を売買する市場)を通じて購入しますが、再エネ価値を求める需要家との直接取引も重要な役割を果たします。現在、新設のFIP電源や2022年度以降に営業運転を開始したFIT電源がFIP電源へ移行した場合、発電事業者と需要家間での直接取引が認められています。
さらに、需要家と発電事業者の直接取引が進展している状況を踏まえ、2021年度以前に営業運転を開始したFIT電源がFIP電源に移行した場合にも、直接取引を可能にする仕組みの導入が検討されています。この議論は関係審議会(制度検討作業部会)で進められる予定であり、非FIT証書の直接取引拡大によってFIP制度のさらなる促進が期待されています。
アグリゲーション・ビジネス等の活性化

アグリゲーターとFIP事業者のマッチング・プラットフォームの設立
FIP制度のさらなる普及を進める上で、小規模事業者をはじめとする再エネ発電事業者がアグリゲーター(集約事業者)と連携を深めることが重要です。アグリゲーターは特定卸供給事業者とも呼ばれ、発電事業者や需要家を束ねる事業者で、需要と供給のバランスを調整する役割を担います。しかし、アグリゲーターは多くの発電事業者にとって必ずしも身近な存在ではなく、このギャップを埋める取り組みが求められています。
この課題に対応するため、アグリゲーターの事業者団体と連携し、全国のアグリゲーターが提供するFIP事業者向けのアグリゲーションプランを公開する仕組みが整備される予定です。具体的には、資源エネルギー庁が公式ウェブサイトでプランを公開し、再エネ発電事業者が簡単にアグリゲーターにアクセスできるプラットフォームを設立することになりました。
この新たなマッチング・プラットフォームにより、再エネ発電事業者が適切なアグリゲーターとつながる機会が増え、FIP制度の利用がさらに促進されることが期待されています。この取り組みは、小規模事業者を含む再エネ発電事業者の効率的な運営を支援し、再エネの市場統合を促進させる重要な施策です。
関係事業者の理解醸成等を促進する勉強会の開催
FIP制度を活用して再エネ発電事業者が安定した収益を上げるためには、関係事業者と連携を深め、発電量や市場価格などの変動予測を効率化・精緻化する必要があります。このため、資源エネルギー庁は「FIP制度の活用促進に向けた勉強会」を開催する方針を打ち出しました。
この勉強会には、再エネ発電事業者をはじめ、気象予測関係者、アグリゲーター、蓄電池事業者、金融機関、小売電気事業者など、FIP制度に関わる多様な関係事業者が参加します。議題ごとに参加希望者を募集し、関連する最新の技術や知識を共有する場として機能します。
資源エネルギー庁の公式ウェブサイト「なっとく!再生可能エネルギー」3では、勉強会の詳細や募集案内が随時公開される予定です。この取り組みにより、関連プレーヤー間の理解と協力が深まり、FIP制度のさらなる普及と効果的な活用が期待されています。
FIP電源の需給調整に資する系統用蓄電池の導入促進
FIP電源の需給調整を担うアグリゲーターにとって、系統用蓄電池の導入拡大は非常に重要です。これまで政府は、さまざまな政策を通じてその普及を支援してきました。2021年度からは補助金制度を導入し、系統用蓄電池の導入を支援しており、これまでに27件が設置されています4。また、2022年には電気事業法が改正され、1万kW以上の系統用蓄電池を「発電事業」として位置付けることで、発電事業者と同様の規制を適用する仕組みを整備しました。さらに、2023年度には脱炭素電源オークションが開始され、系統用蓄電池が支援対象に加えられた結果、初回のオークションでは109万kWが落札されるという成果を挙げています。
今後のさらなる導入拡大に向けては、多くの課題に対応する必要があります。まず、安全性や持続可能性の確保が不可欠であり、系統連系を長期的に支える体制の整備も重要です。また、電力市場での収益性を適切に評価し、蓄電池のユースケースを広く普及させる取り組みも求められています。加えて、長時間の充放電が可能となる新しい蓄電システムの活用についても検討を進める必要があります。
これらの課題を解決することで、系統用蓄電池の導入がさらに拡大し、再エネ電力の需給調整能力が向上することが期待されています。政府のこれらの取り組みは、持続可能なエネルギー社会の実現に向けた重要な一歩となるでしょう。
まとめ
FIP制度は、再エネの普及を加速させる重要な役割を果たしています。これまでの取り組みにより一定の成果が見られる一方で、さらなる普及に向けた課題にも対応が求められています。蓄電池の活用や発電量予測技術の向上、事業者間の連携強化、非FIT証書の取引拡大など、多岐にわたる施策が進行中です。これらの取り組みを通じて、再エネ発電事業の効率化や国民負担の抑制が図られ、FIP制度の活用が一層促進されることが期待されています。政府と関連プレーヤーが協力し、持続可能なエネルギー社会の実現に向けた歩みを加速させることが重要です。
【出典・参考資料一覧】