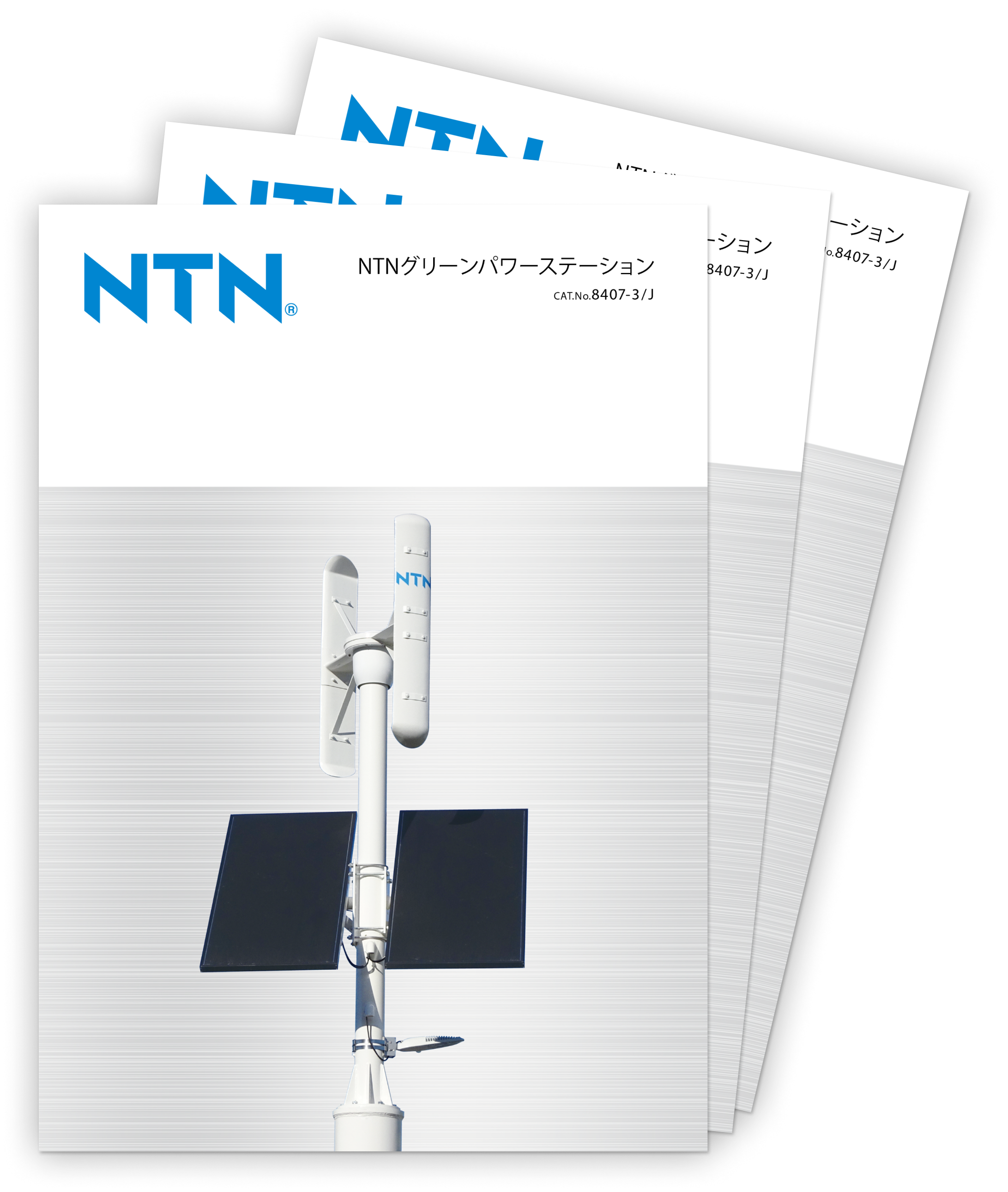再生可能エネルギーの長期電源化および地域共生に向けた検討
日本は、2050年のカーボンニュートラル実現を目指し、再生可能エネルギー(再エネ)の導入を大幅に拡大する方針を掲げており、この目標を達成するため、エネルギー政策の基本である「S+3E」(Safety=安全、Energy security=エネルギー安全保障、Economic efficiency=経済効率性、Environment=環境保護)を前提に、再エネの「主力電源化」を推進する方針が示されています。
国民負担の抑制と地域共生を図りつつ、再エネの最大限の導入が促されることになり、以下に経済産業省の審議会で議論されている具体的な改善点や課題点について紹介します。
土地開発前段階

手続き厳格化の対象となる許認可
太陽光発電の導入を円滑に進めるため、土地開発に関する手続きが厳格化されました。特に、周辺地域の安全を確保するため、事前の許認可取得が義務化され、これを満たさない場合は事業認定が不承認となります。必要な許認可は、森林法に基づく「林地開発許可」、宅地造成及び特定盛土等規制法(旧・宅地造成等規制法)に基づく許可、砂防三法(砂防法・地すべり等防止法・急傾斜地法)に基づく許可の3つです。
森林法に基づく「林地開発許可」は、森林を開発する際に必要なもので、土地の開発に伴う森林伐採や土砂流出のリスクを軽減するために求められます。宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可は、特に斜面や急傾斜地での太陽光パネルの設置時に求められます。不適切な盛土は災害の原因になるため、盛土の規制を強化することで、土砂災害のリスクを未然に防ぐことが目的です。砂防三法に基づく許可は、土砂災害の危険性がある地域での開発に必要なもので、斜面崩壊や地滑りのリスクを低減するために、厳格な審査が求められています。
これまで、事業者は法令遵守を誓約すれば認定が可能でしたが、再エネ特措法改定後は申請時点で許認可の取得が必須となりました。これにより、違法な土地開発や災害のリスクが高まる行為が未然に防がれるようになります。これらの手続きは、FIT制度およびFIP制度の申請要件に組み込まれており、事前の許認可取得がない場合、申請は不承認とされることになります。
関係法令間の手続きにおける整合性への対応
土地開発を行う際には、さまざまな関係法令が絡み合います。そのため、許認可手続きの整合性を図ることが求められます。
例えば、開発までに時間がかかる風力発電や地熱発電における環境影響評価の手続きは、新たに申請要件とする許認可を、認定後に取得できるようにすべきだとされています。ただし、環境影響評価の手続きが完了する前に事業に着手した場合や、認定から3年以内に必要な許認可を取得できなかった場合は、認定を取り消す厳格なルールも設けられました。
また、電気事業法に基づく工事計画や使用前自己確認結果の届け出においても、関係法令の許認可を適切に取得しているかを確認する仕組みの強化が検討されています。今後、具体的な制度の詳細は関係機関の審議を経て決定される予定です。
土地開発後~運転開始後・運転中段階

違反状況の未然防止・早期解消措置の新設
太陽光発電事業において、認定事業者は認定計画に基づき事業を実施する義務があり、認定計画に違反した場合は指導や改善命令を経て認定が取り消されることがあります。しかし、現行制度では違反が続いている間でも、FIT制度(固定価格買取制度)およびFIP制度(フィードインプレミアム制度)による支援が継続されてしまうため、早期の違反解消が進みにくいという課題がありました。
この課題を解消するため、違反の未然防止および早期解消を促進する新たな仕組みが導入されました。その一つが、交付金留保のための積立制度です。この仕組みでは、認定事業者が認定計画に違反した場合、FIT/FIP交付金を留保するための積立義務が課され、違反状態の間は交付金の支払いが停止されます。違反が解消されるか、適正な廃棄が確認されれば、留保されていた交付金は事業者に返還される仕組みです。
積立命令は金銭の処分を求めるものであるため、行政手続法に基づく聴聞や弁明の機会を設ける必要がなく、迅速な措置の発動が可能です。これにより、迅速な対応が求められるケースでも、関係者への速やかな是正指導が行われ、事業者は速やかに改善に取り組むインセンティブが生まれます。
さらに、認定が取り消された場合、違反が発生した時点から認定が取り消される時点までのFIT/FIP交付金の返還が求められる場合があります。返還命令の対象となる金額は、事業者に支払われた交付金の全額であり、これにより、事業者が違反を放置するメリットをなくす仕組みが導入されました。なお、違反の程度や事業者の帰責性に応じて、返還金額が調整される場合もありますが、基本的には原則的な返還が求められるようになっています。
運転中~適正廃棄段階

太陽電池出力増加時の現行ルールの見直し
カーボンニュートラルの実現に向け、再エネの導入比率を引き上げるため、既存の太陽光発電設備の有効活用が求められています。現在、太陽電池の出力が増加する際には、FIT/FIPの基準価格が最新の価格に変更されるルールが適用されていますが、この運用が改められることになりました。
現行の運用では、出力が増加した場合、既存設備の調達価格や基準価格が新しい価格に変更されるため、事業者にとっては負担が大きく、パネルの更新や増設をためらう一因となっていました。しかし、既存の土地や送電系統を有効活用するためには、パネルの増強が必要とされています。
新たな制度では、太陽電池の出力が増加する際、既存の設備部分に関しては価格を維持し、増設分については最新の低い価格が適用される仕組みに変更されました。この見直しにより、事業者は既存の設備を更新したり、出力を増強したりする際の負担が軽減されます。これにより、より多くの事業者が既存設備の有効活用を検討する動機付けが生まれ、再エネの導入拡大が促進されることが期待されます。
大量廃棄に向けた計画的対応
FIT制度の導入以降、太陽光発電設備の導入が進み、多くの事業者が参入しましたが、2030年代後半には多量の太陽光パネルの廃棄が見込まれています。この課題に対応するため、政府は計画的な廃棄対応を推進しています。
まず、太陽光パネルの廃棄費用の積立が義務化されました。2022年4月に施行されたエネルギー供給強靱化法により、再エネ特措法が改正され、2022年7月から太陽光パネルの廃棄等費用積立制度が開始されました。この制度では、事業者が売電収入から解体等積立金を差し引いて積み立てる仕組みが導入され、将来の廃棄費用が事前に確保されるようになりました。
また、廃棄物処理業者に対しても、太陽光パネルの廃棄時に必要な情報の提供が求められています。太陽光パネルは、重金属などの有害物質を含む場合があり、その処理には適切な情報が必要です。産業廃棄物の排出事業者は、廃棄物の処理および清掃に関する法律に基づき、廃棄物の性状や含有物質に関する情報を廃棄物処理業者に提供することが義務付けられています。
現行の事業計画策定ガイドラインにおいては、含有物質に関する情報を廃棄物処分業者に提供することが求められていますが、具体的な情報の内容や時期、対象が定められていないため、詳細なルールを設けるべきだという指摘がなされています。
政府は今後、廃棄物の処理が円滑に行えるよう、情報提供の仕組みをさらに強化する見込みです。
情報提供の改善に加え、リサイクル・適正処理に関する対応の強化も進められています。使用済みの太陽光パネルは、リユースが可能なものも多く含まれており、太陽光パネルに含まれる銀やその他の有用金属は、資源回収の観点からも価値があります。こうした背景を踏まえ、政府はリサイクルを促進するための体制強化を図っています。
地域とのコミュニケーションを義務化

対象範囲の考え方
太陽光発電の導入に際しては、地域住民とのコミュニケーションの不足が原因でトラブルが生じることが多く報告されています。このような背景を踏まえ、資源エネルギー庁は、再エネ発電設備の事業者に対し、地域住民への事前周知を徹底する方針を打ち出しました。
周辺地域や周辺環境へ影響を及ぼす可能性が高い事業については手続きを厳格化する一方で、その可能性が低い事業には柔軟な手続きを求めています。
例えば、50kW以上の高圧電源は、周辺地域への影響が大きいと考えられ、説明会の実施が強く求められます。一方、屋根設置型の太陽光パネルは、影響が限定的であるため、野立て型よりも手続きが緩やかになる可能性があります。また、災害リスクが高いエリアや住民の生活環境に密接する場所に設置される場合は、より慎重な周知が必要です。こうした地域住民への説明の際には、環境への影響や災害防止の措置を含む具体的な情報を住民に提供し、住民の理解を得る努力が求められます。
説明会に関する要件
説明会の開催は、事業者の努力義務で実施する方向で進められています。説明会により、地域住民への周知不足によるトラブルの発生が抑制されることが期待されます。説明会の開催にあたり、不正行為(虚偽申告や暴行・脅迫など)が確認された場合は事業計画を認定せず、事後に確認された場合も、認定を取り消す措置が検討されています。
これにより、説明会の実効性が高まるとともに、地域住民の不安解消に繋がることが期待されます。
事業譲渡の際の手続き強化

事業譲渡の規制態様
太陽光発電事業の譲渡については、現行制度では「変更認定申請」を行うことが求められていますが、新規で事業を開始する場合と同様に地域とのトラブルが生じやすいとの指摘もあることから、検討会の提言では、譲渡時には前事業者の事業実施状態を把握した上での事業引継ぎや、地域への説明会の開催を求めています。
事業譲渡自体を全面的に禁止するのは、営業の自由や財産権の観点から適切ではないため、事業譲渡時の手続きを厳格化する措置として変更認定申請の要件を強化し、説明会の開催や地域住民への事前周知を義務付ける方針が検討されています。
実質的支配者変更の場面における規制
事業者が特別目的会社(SPC)を活用して太陽光発電事業を行う場合、SPCの実質的支配者が変更されるケースがあり、これにより事業者の責任が曖昧になる懸念が生じます。そのため、SPCの実質的支配者が変更された場合も、事業譲渡と同様の変更認定手続きを求め、説明会の実施や地域住民への周知を行う必要があるとされています。
認定事業者の責任明確化
太陽光発電事業では、発電設備の運用を委託または再委託するケースが多く見られます。この場合、事業の実施責任が曖昧になるリスクがあるため、委託先と再委託先も認定基準や認定計画を遵守するよう、認定事業者が委託先と再委託先に対する監督義務を負うことが求められます。
監督不履行があった認定事業者は、認定取消の対象になる可能性があります。さらに、ガイドラインでは、認定事業者と委託先の間で定期的な報告体制を構築することや、再委託時の事前同意の取得を義務付けることが示されています。これにより、事業運営の透明性が向上し、地域住民に対する信頼が高まると期待されています。
関係法令遵守の徹底

非FIT・非FIP案件の対応
FITやFIPの対象外である再エネ事業についても、補助金事業として行われるケースが多く、これらの事業にも再エネ特措法と同等の基準が求められるようになっています。関係省庁と連携し、補助金案件に対しても規律を強化することが求められています。
所在不明事業者に対する規律の徹底
再エネ特措法では、事業者が住所変更を行った場合は届け出が義務付けられていますが、これを怠る事業者も存在します。こうした所在不明事業者に対しては、改善命令や認定取消などの措置が迅速に行われるよう、法的手続きの迅速化が求められています。
具体的には、所在不明事業者に対しては「公示送達」の手続きを活用する方針が検討されています。公示送達は、住所が不明な相手に対しても、官報やウェブサイトを通じて情報を公示することで、法的な通知が成立する仕組みです。この制度を活用することで、事業者が不在でも、行政が必要な措置を迅速に講じることが可能になります。
【出典・参考資料一覧】